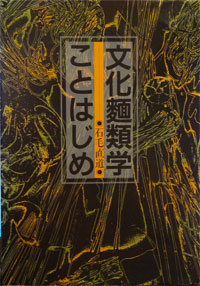露出があってませんね。犯人じゃありません。山下ですw
製麺所のDIYは手を付けたり休んだり、まだ完成にはほど遠いんだけど、あ、そういえば。と思い出して、こんな写真を引っ張り出してきた。
勤めてた会社をやめて、フリーランスになったとき。
自宅で仕事をすることにして、空いてる部屋を仕事部屋に改装しよう、の図。
空いてる部屋?
そう、築30年だか40年だかの家を買って入ったその集落の中では、「完成してしまうと固定資産税が高くなる」とかで、どの家にもそういうできあがっていない部屋があった。我が家もそうだった。

改装前。こうしてみると、わりとまともな部屋だったんだ…
天井は貼ってあったので和室になるはずだったんだな、とわかったけど、畳も当然入ってないし、壁もきわめてテキトーな塗り方。
とても普通には使えないので、物置部屋になってたんだけど、これを改装して仕事部屋にしよう、と。
このころはホームセンターに通うのが楽しくて(今もだけど)、大工道具も一通り持ってた。

改装後。パソコンがたくさんあるなー。VAIO505Xとアラジンの石油ストーブがお気に入りでした。あと、初めて自分で買ったMac – LC745とか。
今の製麺所のDIYと違うのは、この部屋はきっちり長方形だった、ってことかな。でこぼこがたくさんあったり、排水口があったり、そもそも角が直角じゃないところばっかり、という製麺所と比べるとそりゃカンタンだったよね。
あれがえらくスムーズにできたから、ちょっと余計な自信を持っちゃったのかな。
そういえば当時は、ISDNでのデータ通信が毎月定額になるサービスが始まって、自宅で使えるようになるのが待ち遠しかったなぁ。

おまけ。仕事部屋の窓からは、比良山が見えました。雪の比良山はきれいです。
しかしあれだな。10年以上経ってもおんなじことやってる、と。