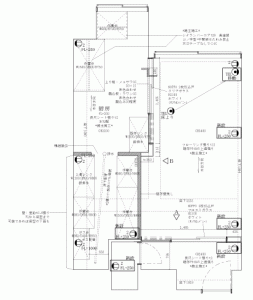うどんを食べるとき、特に、ここのうどんはおいしそうだね!と思ったうどん屋のとき。うどんが出てくるのが待ち遠しくてしかたがない。
運ばれてくるのを今か今かと待ちながら、割り箸だったらあらかじめ割っておいて、どんぶりを置いてもらうスペースもちゃんと空けておいて、うどんがどん!と置かれるやいなやいただきます!を言うのももったいないぐらいに食べ始める。
息をする間も惜しんで、ずるずるずるずると一時も休まず食べ続けて、最後に「はぁ~っ、うまっ!!」とため息と共に幸せ感を口に出す。
うどんって、茹であがった瞬間からどんどん劣化していくから、美味しいうちにはやく食べきってしまいたい、ってあせっちゃうのかな。まぁ、うどんに限らず蕎麦好きな人もそうだろうし、食べ物全般そうだよね。
今でこそそんなことはないけれど、子どもの頃はうどんを一杯食べ終わるとアタマがクラクラすることがよくあった。息をするのを忘れてた、んだと思う。
知り合いからは、「同じうどんを食べてるのに、君の食べてる方が数段おいしく見える」と言われることもある。「噛まないと味わからないんじゃ?」とも。いえ、噛んでるんですよ、時々は。歯ごたえも食味の楽しみの一つだもんね。
いつも残念なのは、急いで食べるからその幸せ感があっという間に終わってしまうこと。もちろん「おいしかった~」って余韻は残ってるけど、もう食べちゃった、っていう残念感の強いこと。
若い頃はかけうどんのあとはざる、そのあとは釜あげ…なんてこともできたけど、最近は時間を空けないと多くて2杯まで。そういう状況も残念感をさらに募らせる。
僕のうどんを召し上がっていただく人たちは、どんな楽しみ方をしてくれるんだろう。
僕はそんな食べ方をするんだけど、普通にゆっくり、あったかいのを、きんと冷えたのを、味わってもらえるとうれしい。小麦粉の味や香りとか、だしの味とか。
一日の中でちょっとだけおいしい彩りをそえられるようなうどんになってくれればいいな。「あぁ、またあのうどん食べて幸せな気分になりたいね」って時々思い出してもらえるような。