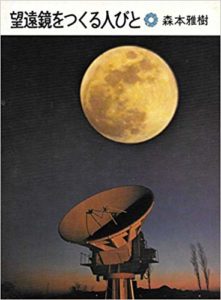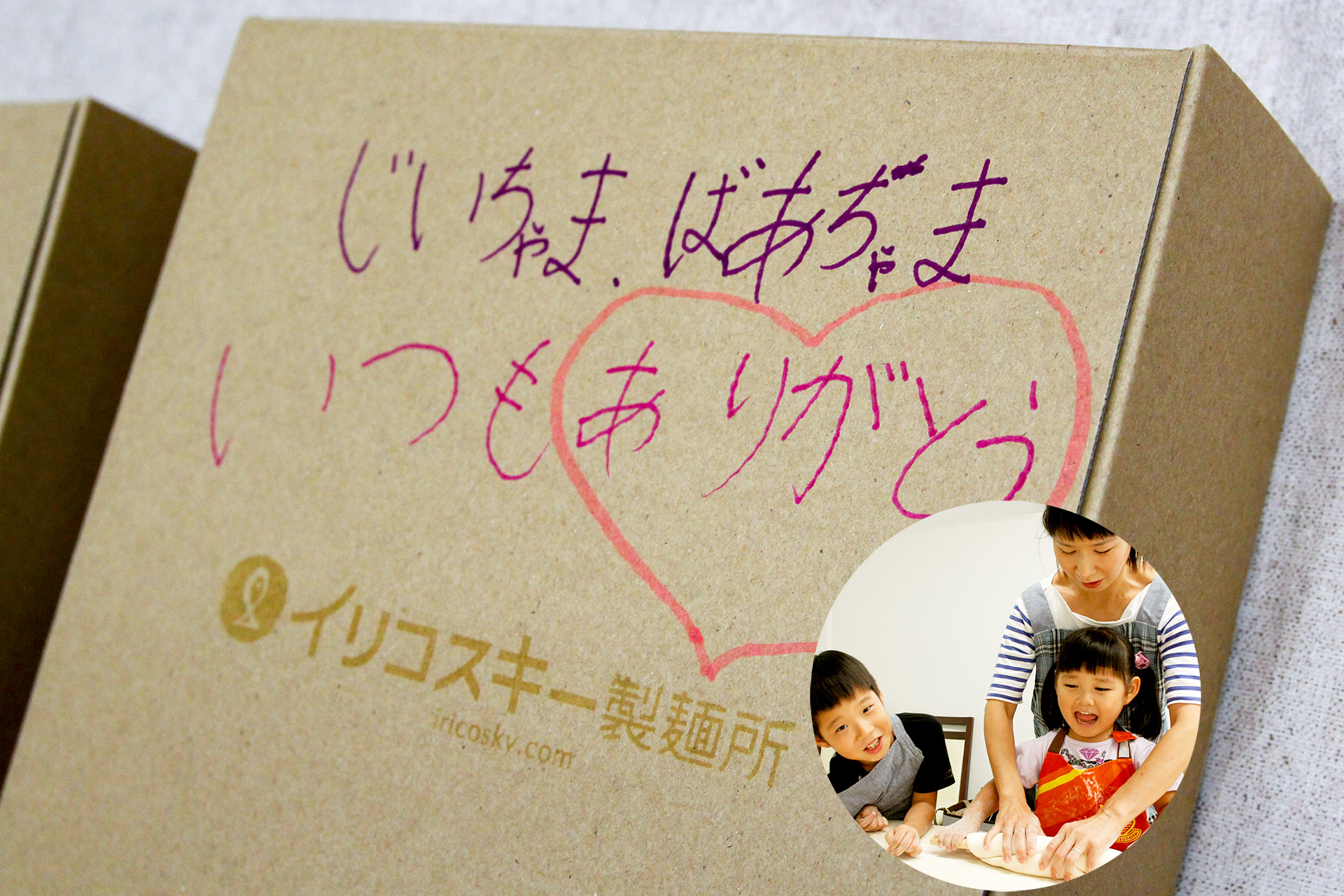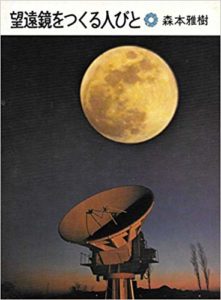
『望遠鏡をつくる人びと』森本雅樹 岩波書店 1972
岩波科学の本シリーズはその後新装版が出たけれど、これは初版だけだったようだ
京都大学岡山天文台に3.8m反射望遠鏡「せいめい」が完成した、という
SNSの投稿を友人がシェアしていた。思い出したのが、ずいぶん昔…おそらく小学生の時に読んだ『望遠鏡をつくる人びと(岩波書店 1972)』だ。
マンガじゃない科学の本にはじめて触れたのがこの本だった。岩波科学の本という中学生向けのシリーズの一冊。
当時父親は息子たちを理系の道に進ませたいと考えていたようで科学に関する本をよく買い与えられていた。
著書は東京大学東京天文台の森本雅樹先生。奥付によると当時は助教授だったようだけれど、この本で覚えた森本先生の名前はその後も書籍や雑誌をはじめいろんなところで見かけることになる。
数式は出てこないとはいえ、歴史に残るそれぞれの時代の最先端の望遠鏡がなぜ作られなければならかったのか、それを製作したのがなぜその人びとだったのか。観測の理論的な考え方や技術的なことも含めて文章と図や写真だけで説明されていくわけで、当時小学生だった僕に理解できたとはとても思えない。
ちゃんと記憶に残っているのは表紙にもなっている、森本先生が深く携わった6メートルミリ波望遠鏡の章と、野辺山につくった最新鋭45メートル電波望遠鏡の章の一部分だ。先生ご自身の苦労話がエッセンスとしてたくさん散りばめられていて、きっと小学生にも身近なものに感じたんだろうな。
観測装置の話だから、夜空にきらめく星のロマンチックな描写や星座の話題は出てこない。天文学者たちが自らの疑問を解き明かす観測を行うために、当時の最先端の技術をいかに使って最新鋭の機材を作り上げたかという話題が並べられる。
この本にも刺激を受けて将来は天文学者になりたい、と僕はその後考え始める。
香川の田舎町の夜空は今よりもずっとはっきりたくさんの星が見えた。父の知り合いから譲ってもらった手作りの望遠鏡を脚立に載せて覗いたり、星座を覚えようとしてみたり、たくさんの書籍を買ってもらったり。
ただ、星座に関するギリシャ神話を読もうとがんばっていたことにも象徴されるように(カタカナの固有名詞がどうにも覚えられなくて悪戦苦闘の連続だった)、子どもが漠然と想像する「天文学者」というものへのあこがれだけを持っていたらしい。
当時は気がついていなかったけれど、きっと僕は天体や宇宙への関心よりも、それを観測するための望遠鏡やロケット、宇宙探査機、そういった機械、機材、メカが好きだったんだな、と今となっては思い返すことが多い。観測される対象や観測手法ではなくって興味があったのは観測機械。
理学部を目指していた僕は、結局高校2年の時文系に舵を切ることになる。あの頃、そこに気がついていれば…理学部じゃなくって工学部のほうが自分の興味にあってるんじゃないの?と考えてみることがあったら、その後の僕はなにか違っていたんだろうか。
ところで、これをブログに書こうと思ったほんとのきっかけは、友人が記事をシェアしたひと月後、9月にたまたま見かけた別のサイトの記事だった。
1970年、大阪万博の年に東京・三鷹に建設されたミリ波望遠鏡は、その後野辺山、水沢、鹿児島へと移設されたのだけれど、2018年10月(まさに今だ!)、三鷹の国立天文台へ里帰りすることになったらしい。
半世紀弱にわたる観測施設としての役目を終えて、日本最初のミリ波望遠鏡を記念する、モニュメント的な施設になるのかな。